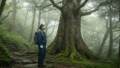福岡市で警備員として働く私が、人生の節目に選んだ旅先は、広島県にある「世界遺産・原爆ドーム」でした。仕事柄、人の安全や命の重さを日々意識している私にとって、この場所はかねてから「一度は訪れたい場所」でした。
静かに佇むその姿には、ただの遺構では語り尽くせない重みがありました。この旅では、原爆ドームの歴史、文化的価値、そして現地で感じたものを、じっくりと記していきたいと思います。
![]()
原爆ドームの場所と気候
原爆ドームは広島県広島市中区、大きな川(元安川)に囲まれた中島地区に位置しています。広島駅から路面電車で20分ほど、平和記念公園の中にあり、川沿いの遊歩道を歩けばすぐにその姿を確認できます。
広島市は瀬戸内海式気候に属しており、年間を通して比較的温暖で過ごしやすいです。私が訪れたのは10月初旬。空気は澄み、日差しも柔らかく、静かな気候が旅を一層深くしてくれました。
![]()
原爆ドームの歴史と特徴
原爆ドームは、もともと1915年に建てられた「広島県産業奨励館」という展示施設でした。チェコ出身の建築家ヤン・レツルによって設計されたこの建物は、当時のモダンなヨーロッパ建築の影響を強く受け、美しいドーム型の屋根とレンガ造りが特徴的でした。
1945年8月6日、世界で初めて人類に対して原子爆弾が投下された日。その爆心地から約160メートルの位置にあったこの建物は、爆風と熱線をまともに受けながらも、完全には崩壊せず、鉄骨と壁の一部を残してその姿をとどめました。
焼け落ちた屋根、骨組みだけになったドーム、黒ずんだ壁。そのままの状態が、今も保存されています。ここに立つと、「あの日」の破壊と苦しみ、そして生き残った人々の証言が一気に胸に押し寄せてきます。
![]()
文化的・宗教的価値
原爆ドームは、戦争の悲惨さと、核兵器の恐怖、そして「二度と繰り返してはならない」という人類共通のメッセージを今に伝える、非常に重要な文化遺産です。宗教的というよりも、むしろ“人間存在に対する問い”を投げかけてくる場所であり、世界中の平和活動家や宗教者たちの祈りの対象にもなっています。
1996年、ユネスコの世界文化遺産に登録された際も、「負の遺産」としての位置づけが話題になりました。しかし、それこそがこの遺構の存在意義であり、世界が共有すべき記憶なのだと、私は現地で確信しました。
![]()
現地で見た詳細な風景と心の動き
原爆ドームは鉄柵に囲まれた中に静かに立っています。その姿は一切の装飾も演出もなく、ただ「ありのまま」。それが逆に、とてつもない説得力を持っていました。
私は警備員として、日常のなかで“当たり前の平和”を守る仕事をしています。しかし、その“当たり前”が一瞬で崩れ去るという現実を、このドームは身をもって教えてくれます。
目を閉じれば、焼け焦げた地面、泣き叫ぶ人々、崩れゆく町。その映像が勝手に頭に浮かんできます。そして今、同じ場所に立ち、穏やかな風を感じることができる。その事実に、言葉にできない感謝が湧き上がりました。
![]()
原爆ドームの年間訪問者数と世界からの関心
原爆ドームを訪れる人の数は、年間でおよそ160万人以上。国内外からの修学旅行生や観光客、そして平和を願う人々がこの地に集まります。特に8月6日には「平和記念式典」が開催され、多くの献花や灯籠流しが行われます。
世界中の人々がこの地を訪れる理由は、「ただの歴史」ではないからです。それは“今も続く問題”であり、未来への問いかけでもあるからです。
![]()
おすすめの旅行ルートと中年警備員の一人旅
今回の私の旅のルートは次の通りでした。
1日目:福岡市 → 新幹線で広島駅へ → 路面電車で原爆ドーム前下車 → 平和記念公園を散策 → 宿泊
2日目:広島平和記念資料館 → 広島城や縮景園を訪問 → 帰路へ
特に資料館は必ず訪れるべき場所です。原爆の恐ろしさを“数字や記録”だけでなく、“人の感情”として受け止めることができる貴重な施設です。
歩いて旅することで、町の空気や人々の生活の中にある“復興の証”も感じ取ることができ、歴史を超えて未来を見つめる旅になりました。
![]()
旅の終わりに感じたこと
原爆ドームは、見る者に「平和をどう守るのか」を問いかける建物です。中年になり、命や人とのつながりの大切さを実感するようになった今、この地を訪れたことには深い意味がありました。
福岡で警備員として働きながら、日々ささやかな“安心”を守っている自分にとって、この旅は「平和とはなにか?」という問いを改めて考えるきっかけになりました。
原爆ドームは、ただの観光地ではありません。それは“未来を変える力を持った遺構”です。
![]()
どうか皆さんも、静かに立ち止まり、考えてみてください。
この場所から生まれた無数の涙と祈りの先に、どんな未来を描くべきか。
中年の旅人として、私は今、静かにその答えを探しています。
![]()